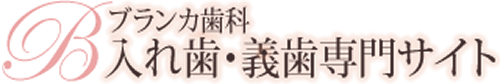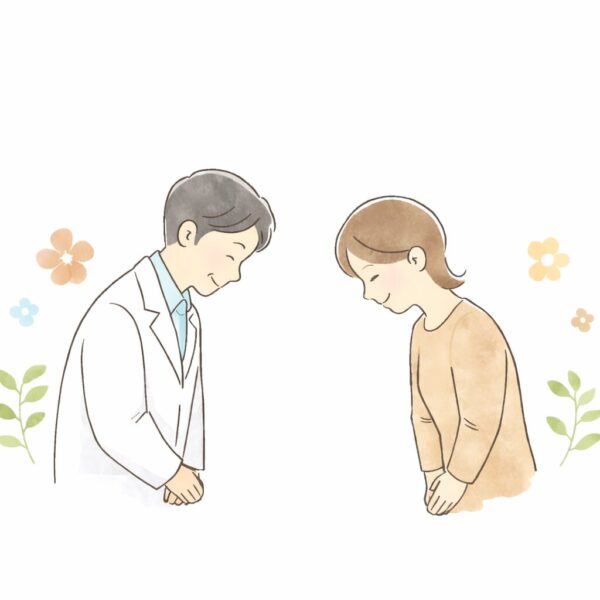🦷 噛む力と全身の健康 ― 咬合が身体にもたらす影響
「子育てには終わりがあるけれど、介護にはいつ終わるかが見えない。」
ある患者さんがおっしゃったこの言葉は、私たちが向き合う“高齢社会の現実”をよく表しています。
介護は突然始まり、そしていつ終わるのか誰にもわかりません。
だからこそ、「介護に入る時期をいかに遅らせるか」が本人にも家族にも大きな意味を持ちます。
その入口に深く関わるのが「噛む力(咀嚼)」です。
近年、噛む力と姿勢・歩行・認知機能・転倒リスクなどとの関係が研究で次々と明らかになっています。
■ 咀嚼力が低下すると、姿勢や歩行が不安定になる
高齢者を対象とした研究では、
・咀嚼力が弱いほど立ち上がり動作が遅くなる
・歩行が不安定になる
・つまずきやすくなる
と報告されています。
咀嚼は顎だけでなく首〜体幹の筋肉が連動する“全身運動”です。
噛めることは姿勢やバランンスを維持するための重要な働きを持っています。
実際の臨床でも、義歯の調整で
・姿勢が良くなった
・歩行が安定した
・ふらつきが減った
と感じる患者さんを多く経験しています。
■ 介護が必要となる原因のトップ3
厚生労働省(2022年)の統計では、要介護の原因は以下の通りです。
1. 認知症:23.6%
2. 脳血管疾患(脳卒中):19.0%
3. 骨折・転倒:13.0%
実はこれら **トップ3すべてに「噛むこと」が関わっています。**
■ ① 認知症と咀嚼
噛むことで前頭葉・海馬が刺激され、脳血流が増えることがわかっています。
咀嚼力が低い高齢者では認知機能が低下しやすいという報告もあります。
■ ② 脳血管疾患と咀嚼
噛めない → 食事量低下 → 低栄養 → 筋力低下
これらは脳血管疾患の大きなリスク要因です。
■ ③ 骨折・転倒と咀嚼
咀嚼力が弱い人はバランス能力が低下し、転倒リスクが高いことが研究で示されています。
■ 70歳を超えると、介護は“他人ごと”ではなくなる
厚労省データでは
・80〜84歳:26%
・85歳以上:60%
が要支援・要介護状態です。
この数字からわかるのは、
**80代で一気に介護率が跳ね上がる**という現実です。
だからこそ、
**歯を失ったり噛めなくなった70代の段階で「適切な治療の手を打っておく」ことが極めて重要**です。
70代はまだ体力・筋力・認知機能の回復力が十分にある年代です。
この時期に噛む力をしっかり確保しておくことで、
80代で迎える大きな介護リスクの波を“どれだけ先送りできるか”が変わります。
■ 噛める → 食べられる → 体力が保てる → 転ばない → 介護が遅れる
これは研究結果と臨床経験の両方が示す事実です。
噛めるようになることで
・食べられる食品数が増える
・筋肉量が維持される
・認知機能も保たれる
・転倒しにくくなる
結果として **介護の開始が遅れる可能性** があります。
義歯治療は「歯の治療」ではなく、
生活の自立・介護予防・健康寿命の延伸に直結する医療です。
■ 来月から深掘りシリーズが始まります
12月以降は、
・70歳以上で介護が急増する理由
・女性の介護期間と噛む力の関係
・栄養と筋肉量と咀嚼
・転倒・骨折と義歯
・認知症と噛む力
を丁寧に解説していきます。